追加融資を断られたらどうする?考えられる理由と対処法を徹底解説
- 名古屋創業融資サポートセンター

- 2025年7月24日
- 読了時間: 15分
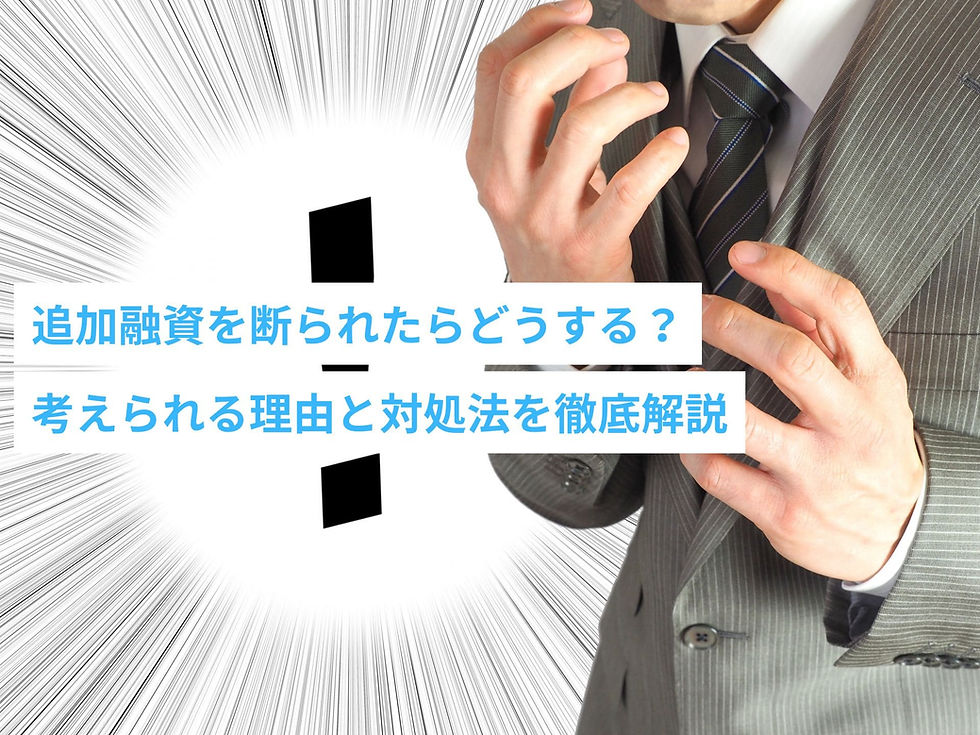
「追加融資を申し込んだのに、断られてしまった…」そんな状況に直面し、資金繰りに頭を抱えていませんか?
事業を継続するうえで、追加融資は大きな支えとなる資金調達手段のひとつです。しかし、一度融資を受けた後でも、再度の申請で断られるケースは少なくありません。特に、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関は、返済能力や事業の継続性を厳しく見極めたうえで審査を行っており、「なぜ断られたのか分からない」と戸惑う方も多くいらっしゃいます。
ただし、追加融資が通らなかったからといって、資金調達の道が完全に閉ざされたわけではありません。その背景にある原因を正しく理解し、改善すべきポイントに対応することで、再申請や他の資金調達手段を通じて道が開ける可能性は十分にあります。
本記事では、追加融資が断られる主な理由や、その後に取るべき具体的な対策、再チャレンジに向けた準備のポイントを解説していきます。また、融資サポートの専門家による無料相談の活用方法についてもご紹介します。
追加融資が断られる主な理由
一度は融資に成功したにもかかわらず、再度の融資申請で断られてしまうケースは少なくありません。金融機関は、初回融資以上に慎重に審査を行うため、ちょっとした準備不足や事業状況の変化が審査結果に大きく影響します。以下に、追加融資が否決されやすい主な理由を解説します。
業績の悪化(売上減少・赤字決算)
金融機関は、返済能力の継続性を重視します。前回の融資実行後に売上が減少したり、赤字決算となっていたりする場合、追加融資は難しくなる傾向にあります。「売上が一時的に落ち込んだだけ」と主張しても、数字としての実績が伴わなければ信用は得られません。特に2期連続の赤字や債務超過状態の場合は、融資審査が一層厳しくなります。
既存融資の返済遅延や信用情報の問題
現在の借入金において、返済の遅延や滞納があると、新たな融資はほぼ不可能になります。また、税金の未納や社会保険料の滞納もマイナス評価につながります。金融機関は「返済を継続できるか」という視点で厳しく見ており、信用に傷があると追加融資は難航します。少なくとも直近1年間は、全ての支払いを期日どおりに履行することが求められます。
資金使途や事業計画に具体性がない
融資審査では、「なぜその資金が必要なのか」「何に使うのか」が明確である必要があります。「とりあえず運転資金が欲しい」では通りません。明確な資金使途が示されていなかったり、収支計画に根拠がなかったりする場合、事業の見通しが不透明と判断されます。数値根拠のある事業計画書や売上予測、具体的な見積書の添付などが重要です。
借入依存度が高く、自己資金が乏しい
創業時にフルローンで融資を受けた方や、自己資金をほとんど入れていない方は要注意です。「自分のお金を使わずに、金融機関の資金だけで経営している」ように見えると、経営者としての信用が下がる恐れがあります。金融機関は「経営者としての責任感」や「資金管理能力」も重視するため、追加融資においては一定の自己資金投入実績やコスト削減の努力が求められます。
前回の融資からの期間が短すぎる
前回の融資から数ヶ月しか経っていない場合、金融機関は「前回の融資で何を達成したのか」を重視します。短期間で再度申し込むと、「資金使途の見積もりが甘かったのでは?」と疑念を持たれる可能性が高まります。特に公庫よりも民間銀行の方がこの傾向が強く、「前回資金の活用実績」がないまま再申請しても、審査は厳しくなります。
追加融資を断られた場合の対処法・解決策
追加融資を断られたからといって、資金調達の道が完全に閉ざされるわけではありません。審査に落ちた原因を把握し、適切な対応をとることで再申請や他の手段で資金を確保できる可能性は十分にあります。ここでは、具体的な対処法と解決策をご紹介します。
原因を分析し、事業計画や財務内容を見直す
まず最初にすべきことは、なぜ追加融資が通らなかったのか、その原因を見極めることです。金融機関からは具体的な否決理由が明示されない場合がほとんどですが、申請内容や現状を客観的に見直すことで、改善すべき点が見えてきます。
売上や利益が大幅に下がっていないか
借入金の返済状況は問題ないか
資金使途は明確か
事業計画書に根拠となる数値はあるか
これらの点をチェックし、説得力のある事業計画と、資金使途に沿った適正な融資額の申請を心がけることが重要です。
時間を置いてから再申請する
すぐに再度申し込んでも、状況が変わっていなければ結果は同じです。一般的には6ヶ月程度の期間を空け、財務状況の改善や自己資金の積み増しを行ったうえで再チャレンジするのが望ましいとされています。
この期間に、たとえば売上回復や黒字化を実現すれば、前回の審査とは違う結果が期待できます。再申請の際は、前回の反省点を踏まえた修正計画を盛り込むことが重要です。
他の金融機関に相談してみる
一つの金融機関で断られても、他の金融機関では融資が受けられる可能性があります。特に日本政策金融公庫で否決された場合でも、地元の信用金庫や民間銀行が前向きに検討してくれることもあります。
融資姿勢や審査基準は金融機関によって異なるため、1社で断られたからといって諦めるのは早計です。異なる機関に相談する際は、前回の申請内容を見直し、改善点を明確にしたうえで臨みましょう。
ノンバンクのビジネスローンを検討する(注意が必要)
急ぎで資金を調達したい場合、アコムやアイフルなどのノンバンク系ビジネスローンを活用するという方法もあります。これらのローンは審査が比較的柔軟で、赤字決算や自己資金が乏しい場合でも通る可能性があります。
ただし、金利が高く返済負担が重くなる点には注意が必要です。あくまで緊急避難的な手段として利用し、長期的な資金繰りには適していないことを理解しておくべきです。
ファクタリングの活用
もし売掛金がある場合は、ファクタリングで早期に現金化する方法もあります。ファクタリングは融資ではないため、信用情報に影響を与えにくく、審査に通らなかった企業でも利用できる可能性があります。
ただし、手数料が高め(10〜20%程度)になることが多いため、慎重に検討する必要があります。短期的な資金ショートの対策として、計画的に利用することが求められます。
補助金・助成金など他の資金調達手段を探る
融資以外にも、中小企業や個人事業主向けに各種の補助金・助成金制度が設けられています。こうした制度は、申請要件を満たせば返済不要で資金を得られる貴重な手段です。
また、クラウドファンディングや資本性ローン(出資型融資)など、自己資金や借入以外の資金調達方法を検討するのも有効です。制度の選定や申請のアドバイスについては、専門家に相談することでスムーズに進められます。
融資サポートの専門家に相談するメリット
追加融資を断られたあと、原因の分析や再申請の準備を自力で行おうとしても、何から手を付ければよいか分からず、行き詰まってしまう方も少なくありません。そんなときは、融資支援に精通した専門家に相談することが、再チャレンジ成功の近道になります。
ここでは、融資サポートの専門家に相談することで得られる主なメリットをご紹介します。
書類や計画書の「落とし穴」を見抜ける
融資申請に必要な事業計画書や資金繰り表などの書類は、一見正しく書けているようでも、金融機関から見たときに「説得力が弱い」と判断されてしまうことがあります。融資の専門家であれば、審査側の視点に立って事前に改善点を洗い出し、通りやすい内容にブラッシュアップすることができます。
特に、以下のような修正は専門家の得意分野です。
数値根拠の補強(売上予測・利益計画)
資金使途の明確化
希望融資額の妥当性チェック
収支計画の整合性
「あと一歩で通るはずだったのに…」という惜しい否決を防ぐためにも、プロによる書類チェックは非常に有効です。
金融機関が重視するポイントを押さえた対策ができる
融資サポートの実績がある専門家は、日本政策金融公庫や銀行の審査基準や担当者の考え方をよく理解しています。そのため、融資担当者の評価につながるような計画書の作成やプレゼン方法を的確に指導することができます。
たとえば、
「なぜ今、追加資金が必要なのか」
「その資金でどう売上や利益が伸びるのか」
「返済はどう担保されるのか」
といった、審査担当者が最も知りたいポイントを論理的に説明する構成づくりが可能になります。
最適な金融機関や制度を提案してもらえる
「公庫に断られたから、もうどこも借りられない」と諦める必要はありません。専門家に相談すれば、事業規模や地域性、業種などを考慮した最適な融資先や制度を提案してもらえることがあります。
たとえば、
地域の信用金庫による制度融資
商工会議所のマル経融資
民間保証付き融資(信用保証協会利用)
など、自分では気づかない選択肢が見つかる可能性があります。また、最近では金融機関とのつながりを活かして、紹介・事前ヒアリングをセットで行ってくれる専門家も増えており、融資通過率を高めるうえで心強い存在となります。
面倒な手続きや不安を軽減できる
融資申請は、必要書類の準備、計画書の作成、金融機関とのやりとりなど、手間と時間がかかる作業が多く、経営者にとって大きな負担になります。専門家に依頼すれば、これらの作業を代行・サポートしてもらえるため、本業に集中しながら融資準備が進められます。
さらに、「次も落ちたらどうしよう」といった精神的な不安も、専門家と二人三脚で進めることで大きく軽減されます。一人で悩みを抱え込まず、客観的なアドバイスを受けながら冷静に対策を立てることができるのも、大きなメリットです。
追加融資を断られたケース例(事例紹介)
ここでは、実際に追加融資を断られたものの、専門家のサポートを受けて資金調達に成功したケースをご紹介します。「自分にも当てはまるかも」と感じられるような実例を知ることで、読者自身の次のアクションに役立てていただけます。
事例①:創業2年目の飲食店が追加融資を断られたケース
<背景>
名古屋市内で飲食店を経営するAさんは、創業時に日本政策金融公庫から300万円の融資を受けて開業。開業後1年半が経過し、事業も軌道に乗っていたため、厨房機器の入れ替えと新メニュー導入のため、追加融資200万円を申請しました。
<問題点>
しかし審査の結果は否決。理由の詳細は告げられませんでしたが、後から振り返ってみると、
前期の決算がわずかに赤字だった
資金使途が漠然としていた
自己資金の積み増しがなかった
という点が審査上マイナスに働いていたと考えられました。
<専門家に相談して改善した点>
Aさんは地域の融資サポート専門家に無料相談を依頼し、以下のような改善を行いました。
赤字の原因を明確化し、原価率改善計画を立案
具体的な設備の見積書を添付し、費用対効果を数値で説明
売上回復の傾向と将来の収益見通しを根拠をもって提示
個人資金50万円を追加で投入し、自己負担の姿勢を示した
これらを踏まえて、3ヶ月後に地元の信用金庫にて制度融資に再チャレンジし、希望額とほぼ同額の200万円の融資が実行されました。
<ポイント>
一度断られても、「なぜ通らなかったか」を正しく理解し、対策を講じれば、資金調達の道は十分に開けるという好例です。
事例②:設備投資で公庫に断られた製造業者が別ルートで成功
<背景>
B社は創業4年目の製造業。新規の大口取引に対応するため、追加の機械設備導入を計画し、公庫に500万円の融資を申し込んだが否決されました。
<問題点>
公庫審査では、以下の点がネックになっていたと推察されました。
自己資金の投入がゼロ(フルローン申請)
売上予測の根拠が弱く、契約書などの裏付け資料がなかった
前回融資の残債が多く、返済比率が高かった
<改善後の流れ>
B社は専門家のアドバイスにより、次のような対応を行いました。
取引先から内示書を取得し、確度の高い売上予測を提示
社長個人から100万円の資金を事業に投入
前回融資との返済シミュレーションを作成し、月次収支との整合性を説明
結果として、地元の商工会議所を経由し、「マル経融資制度(小規模事業者経営改善資金融資)」で希望額に近い450万円の融資を獲得。月額返済も無理のない計画となり、事業拡大への一歩を踏み出しました。
事例から学べること
断られた原因の分析と資料の精度向上が重要
自己資金の投入や経営者の熱意は大きな評価ポイントになる
別の融資制度や金融機関への切り替えも有効な選択肢
一度の否決で諦めず、状況を整えて再チャレンジする姿勢が大切です。そしてその際には、融資に詳しい第三者の視点を取り入れることで、突破口が見えてくる可能性が高まります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、追加融資を断られた方からよく寄せられる質問と、その回答を分かりやすくまとめました。同じ悩みを抱える方が次の一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。
Q1:一度断られたら、もう同じ金融機関で融資を受けるのは無理ですか?
A:いいえ、再チャレンジは可能です。日本政策金融公庫や銀行で追加融資を断られた場合でも、一定の条件を整えれば再申請することは可能です。ただし、前回と同じ内容・状況で短期間のうちに再度申し込んでも、審査通過の可能性は低いといえます。
少なくとも数ヶ月以上の期間を空け、赤字解消や売上改善、自己資金の増強などの「変化」を示すことが重要です。再申請のタイミングや改善点について不安がある場合は、専門家に相談して方向性を確認しましょう。
Q2:前回の融資から半年も経っていません。それでも申請していいのでしょうか?
A:タイミングには注意が必要ですが、絶対にNGというわけではありません。たとえば、前回の融資で成果が出ていて、追加の資金使途が明確かつ合理的であれば、短期間でも追加融資が通る可能性はあります。
ただし、一般的には「返済実績」や「前回資金の活用状況」がある程度蓄積されているほうが好ましいとされており、半年未満での申請はややリスクが高めです。慎重に判断した上で、事業計画書に客観的な根拠や数値をしっかり盛り込むことがカギとなります。
Q3:公庫に断られましたが、銀行や信用金庫で通る可能性はありますか?
A:はい、あります。金融機関ごとに審査基準やリスクの捉え方は異なります。日本政策金融公庫での否決が、民間金融機関にとって必ずしもマイナスとは限りません。
むしろ、「公庫でダメだったならうちで支援しよう」という姿勢を示す信用金庫などもあります。ただし、公庫で否決された理由をしっかり分析し、改善点を反映させた申請が必要です。
Q4:自己資金がほとんどないのですが、追加融資を受けられますか?
A:自己資金がゼロの場合、追加融資はかなり難しくなります。金融機関は、経営者の資金的なリスク負担や覚悟も評価対象に含めます。そのため、自己資金をまったく入れていない状態での追加融資申請は「依存体質」と見なされてしまう可能性が高いです。
まずは、少額でも構わないので自己資金を積み立てる姿勢を見せることが大切です。また、利益を内部留保として貯めておくなど、資金の蓄積を証明できるよう準備することが再審査の成功につながります。
Q5:融資がどうしても難しい場合、他に資金調達の方法はありますか?
A:はい、複数の選択肢があります。融資以外にも、以下のような資金調達方法が考えられます。
ファクタリング:売掛金を早期に現金化できる。ただし手数料が高め。
補助金・助成金:返済不要の制度も多く、条件が合えば活用価値は大きい。
ノンバンクのビジネスローン:審査が柔軟だが、金利は高め。短期的な利用に限るべき。
クラウドファンディングや知人からの出資・借入などの私的な手段も、状況によっては有効。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合った手段を見極めることが重要です。判断に迷う場合は、資金調達に詳しい専門家に相談しながら方向性を定めることをおすすめします。
まとめ
追加融資を断られると、事業の継続や拡大に大きな不安を感じるかもしれません。しかし、一度の審査落ちが「資金調達の終わり」ではないことを知っておくことが大切です。
多くの場合、融資が否決される背景には、事業計画の不備や収支の根拠不足、資金使途の曖昧さなど、改善可能な要素が潜んでいます。また、金融機関ごとに審査基準は異なるため、公庫で断られても他の制度や銀行でチャンスがあるケースも珍しくありません。
そして何より、融資サポートに精通した専門家に相談することで、原因の特定や改善点の明確化、再申請の成功率を大きく高めることができます。書類のブラッシュアップ、金融機関との交渉方法の指導、適切な制度の選定など、専門家のサポートがあれば、再チャレンジに向けた準備を着実に進めることが可能です。
資金繰りに不安を感じている方こそ、早めの相談と冷静な対処がカギとなります。事業の未来を守るためにも、今できることから行動を始めてみましょう。
融資の不安は一人で抱え込まず、専門家にご相談ください
「追加融資を断られてしまった」「このままでは資金が尽きるかもしれない」と感じている方へ。まずは落ち着いて、今の状況を整理し、専門家と一緒に最適な道を考えてみませんか?
税理士法人伊勢山会計では、個人事業主・中小企業経営者・創業予定者の方を対象に、融資に関する無料相談を行っています。
なぜ融資が通らなかったのか知りたい
再申請を検討しているが自信がない
他の資金調達方法を探したい
書類のどこを直せばいいか分からない
このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。状況を丁寧にヒアリングしたうえで、再申請の可能性や改善ポイント、他の融資制度の選択肢までアドバイスいたします。
相談はオンライン・対面どちらにも対応しており、ご相談は無料です。無理な営業は一切いたしませんので、「今後どう動けばいいのか分からない」方こそ安心してご利用いただけます。



コメント